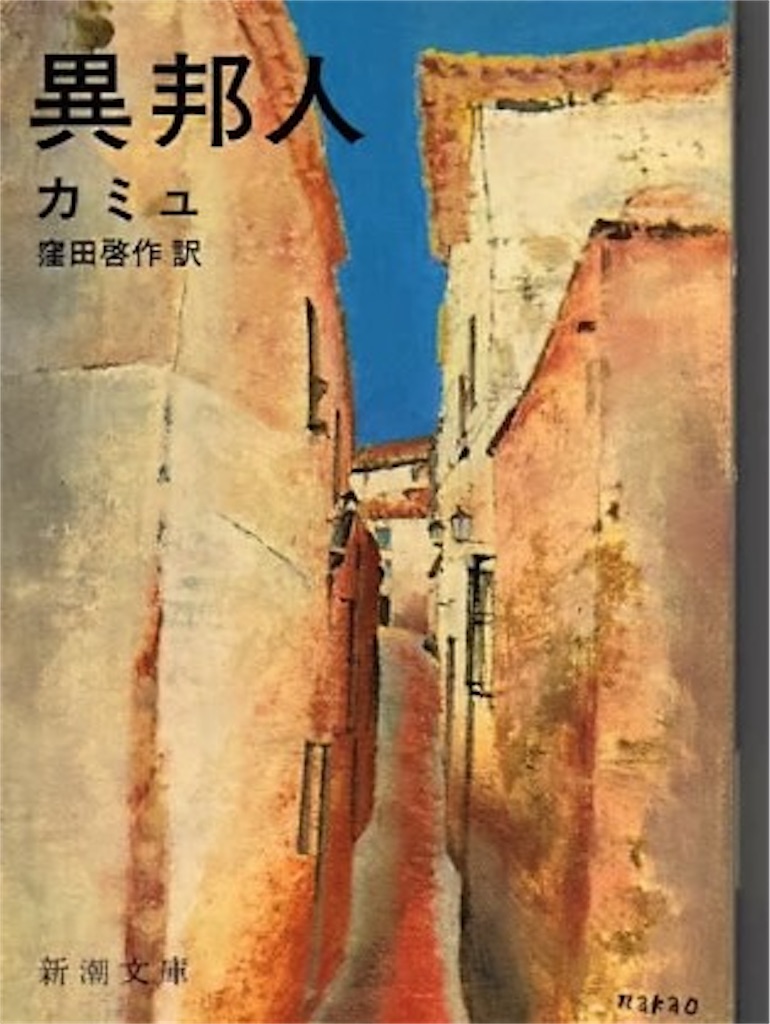
ノーベル賞作家、
アルベール・カミュの代表作、
確か学生の頃に課題か何かで購入したもの、
書棚を漁っていると出てきたので、
ふと手に取るとそのまま最後まで読んでしまった。
テーマはとても多様な解釈ができる。
私の解釈では、
「アナキストの視点から社会における不条理と同調圧力の滑稽さを浮き彫りにする」
というところか。
アナキストと言っても、
いわゆる「無政府主義者」ではなく、
心の拠り所を持たない「無神論者」に近いか。
それが表題の所以だと感じる。
以下あらすじ、
世界に無頓着、
というよりは社会に無頓着というべきか。
亡くなった母の葬儀を淡々と済ませ、
涙一つ流さない。
悲しみにくれるでもなく、
翌日には恋人と喜劇映画を見て、
情事に耽る。
だけれども自然に安らぎを感じたり、
自らの理をもっている。
それが社会の常識とは一線を画しているだけ、
そんな無味無臭な主人公の男、
その視点で語られる「生と死」「社会の滑稽さ」
その緻密な描写はとても読み応えがあった。
ある日、主人公は事件を起こす。
友人と恋人と海水浴に出掛けた先で、
危ない仕事をしている友人を恨む男が襲い掛かる。
そのやり取りの中で、
主人公は相手の男が構えた刃物を照らす、
太陽の光に正気を失ったかのように男を銃殺してしまう。
そうして逮捕され、
何もかもを失い自由を奪われながらも、
その生活の中でも自らの理を曲げずに、
ささやかな自由に身を投じて淡々と生きる。
自らの裁判をどこか俯瞰して見ており、
「私の裁判なのに私のいる必要などないように淡々と進む」と評する。
動機を「太陽が眩しかったから」と言い放ち、
母が亡くなっても悲しみ一つ見せない態度や、
裁判中の不遜な態度を反省の色無しと判断され、
判決は「死刑」
何度も神父が訪ねて懺悔を進めるも、
彼は「神など信じていない」と拒否、
そんな彼が唯一感情を露わにしたのは、
神父のしつこさと神を絶対視して止まない態度だ。
たとえ牢獄にあっても、
自分の心は何者にも縛られない。
そのような主張をして神父を罵った後に、
妙な悟りを得た彼は、
処刑台にて嘲りと恫喝を浴びせられることを、
今生最後の望みとして命尽きるその時を待つ、
処刑を前にしても彼の心は安らぎに満ちていた。

『異邦人』
そのタイトルは、
「人とは異なるもの」
「人ではないもの」
そのような意味が込められている。
当時の西欧社会を鑑みると、
「神を信じないもの」と言い換えられる。
今で言えば「社会を信じないもの」か。
同調圧力をものともせずに、
「空気」だとか「雰囲気」を読まない人、
そんな人が現代の「異邦人」に当たるのだろう。
「全く忖度をしない」
それが「異邦人」
持ちつ持たれつの歪な関係で繋がれた社会、
半ば「空気を読むこと」が当たり前となっている。
1942年に書かれた作品だけれども、
当時の西欧でもそのような空気に支配されていたのだろうな。
人間は多様性を持つ生き物だ。
知恵を身につけたばかりに、
育ってきた環境が他の生物の比にはならないほど複雑に絡み、
各々の性質を作り上げる。
「自分らしく生きること」と、
「人間らしく生きること」
一個人に置いて、
必ずしもそれが一致するとは限らないのだ。
だけれども「人間らしさ」
そういう社会規範というルールを作る側から見て、
「異質」とされたならば「排除」の対象になる。
ルールに守られるからには、
ルールを守る必要がある。
そうやって人は、
自らを守るとともに自らを殺し、
生きやすくすると同時に、
生きづらい環境を手に入れた。
本作では「殺人」という、
センセーショナルな書き方をしている。
それはもちろん罰せられるべきだ。
しかし組織にいると、
必要かどうかもわからない同調圧力、
そういうものにうんざりすることはたくさんある。
「自分らしさ」を貫くことで社会に殺される。
そういう大きくなりすぎた同調圧力に、
一石を投じる作品なんじゃないかな。
主人公像は純文学のそれだ。
無味無臭な主人公の視点から描く社会風刺、
村上春樹作品に通じるものがある。
確か『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』の中で、
本作に言及していたはずだ。
ただ村上春樹作品と決定的に違うのは、
「市井の人」ではないこと、
村上春樹作品の主人公は総じて、
小賢しいけれど小市民だ。
大きな傷を抱えていて、
それと生真面目に向かい合いながら生きている。
無感情に人を殺めることはまずない。
ただ多くの作家が影響を受けた作品であることは、
間違い無いのだろう。
本作をお薦めするかと問われると、
とても迷う作品だ。
諸刃の剣みたいな危険な香りのする作品でもある。
ただはっきりと言えることは、
その時代に爪痕を残し、
時の洗礼を受けても色あせない名作ということだ。
余談だけれども、
久保田早紀さんの代表曲『異邦人』は、
おそらく「旅先での行きずり相手」というような意味、
「地元ではない人」ということだろう。
これもまた情緒のある名曲、
前に中島みゆきさんの『ファイト!』でも動画をリンクした歌い手さんが歌っていた。